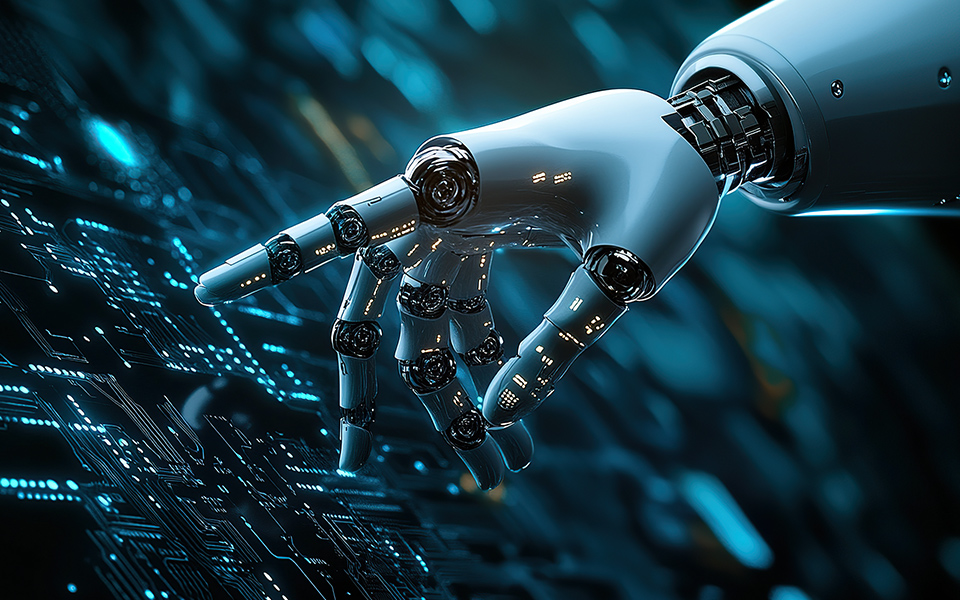Glossary 用語集一覧
用語集一覧
全 663 件 見つかりました。
-
核磁気共鳴分光法
【unclear magenetic resonance spectroscop】"原子核のスピンを利用して物質の構造・状態を非破壊的に知る方法。核スピンを持つ原子核を強い磁場の中に置くと、核スピンが磁場と平行、または逆報告の2つのエネルギー状態に分裂し、そのエネルギー差に対する波長の電磁場を吸収するようになる。このエネルギー差は、その原子核の周辺の電子の分布や原子の結合状態に影響され、それが共鳴吸収スペクトルとして観測される。主に対象となる元素は水素、炭素であり、有機化合物の同定や構造決定に用いられる。
-
共振抵抗
粘弾性変化の指標となる値。単位:Ω
-
空間線量率
単位時間あたりの放射線の量、単位はμSv/h(マイクロシーベルトパーアワー)
-
空気電池
燃料電池の一種。正極に空気中の酸素を使用し、負極に金属(マグネシウム等)を用いる。金属マグネシウムを太陽炉で還元することで、クリーンでリサイクル可能な電池として注目を集めている。空気マグネシウム電池、マグネシウム燃料電池とも呼ばれる。
-
結合剤噴射
けつごうざいふんしゃ【Binder Jetting】粉末床に結合剤を噴射して選択的に固体化する。
-
高周波焼入れ
【Induction hardening】高周波誘導電流を利用して鋼材の表面だけを急速に熱し、急速に冷やすことで表面を硬化させる金属処理のこと。 耐疲労度と耐摩耗性に優れ、歯車やシャフト、平板などの機械部品の焼入れに適している。 表面だけの加工、一部分だけの加工が可能なので、部品の変寸や変形のリスクを最小限に抑えられることが特徴。 また、表面もきれいに仕上がり、部品の品質も安定する。
-
材料押出
ざいりょうおしだし【Material Extrution】 液体もしくは可塑化された個体をノズルから押出し堆積すると同時に固体化する。別名:FDM(溶融物堆積法)
-
材料噴射
ざいりょうふんしゃ【Material Jetting】液状の材料をノズルから噴射し堆積した後に固体化。
-
仕事関数
シゴトカンスウ 【work function】"物質表面から1個の電子を取り出すのに必要な最小エネルギーのことです。単位はeV(エレクトロンボルト) これが大きい物質は、電子が出にくい、つまり、電子が余っていない、ということになります。小さいものは、電子が余っているということです。 仕事関数は表面の電子状態に強く依存している量です。その意味で、仕事関数は表面の研究において非常に重要な物理量の一つです。実験的には、ケルビン法(振動容量法)、熱電子放出や光電子放出実験などで測定されます。 例:有機ELの電極などは,仕事関数の小さい物質を使った方が少ないエネルギーで発光させられます。"
-
二次電子
ニジデンシ【secondary electron】固体に外部から電子を打ち込むとき、固体内の電子が励起され放出されたもの。走査型電子顕微鏡(SEM)では、50eV以下のエネルギーで放出されるものを二次電子といい、これを主に検出する二次電子像を観察することが多い。